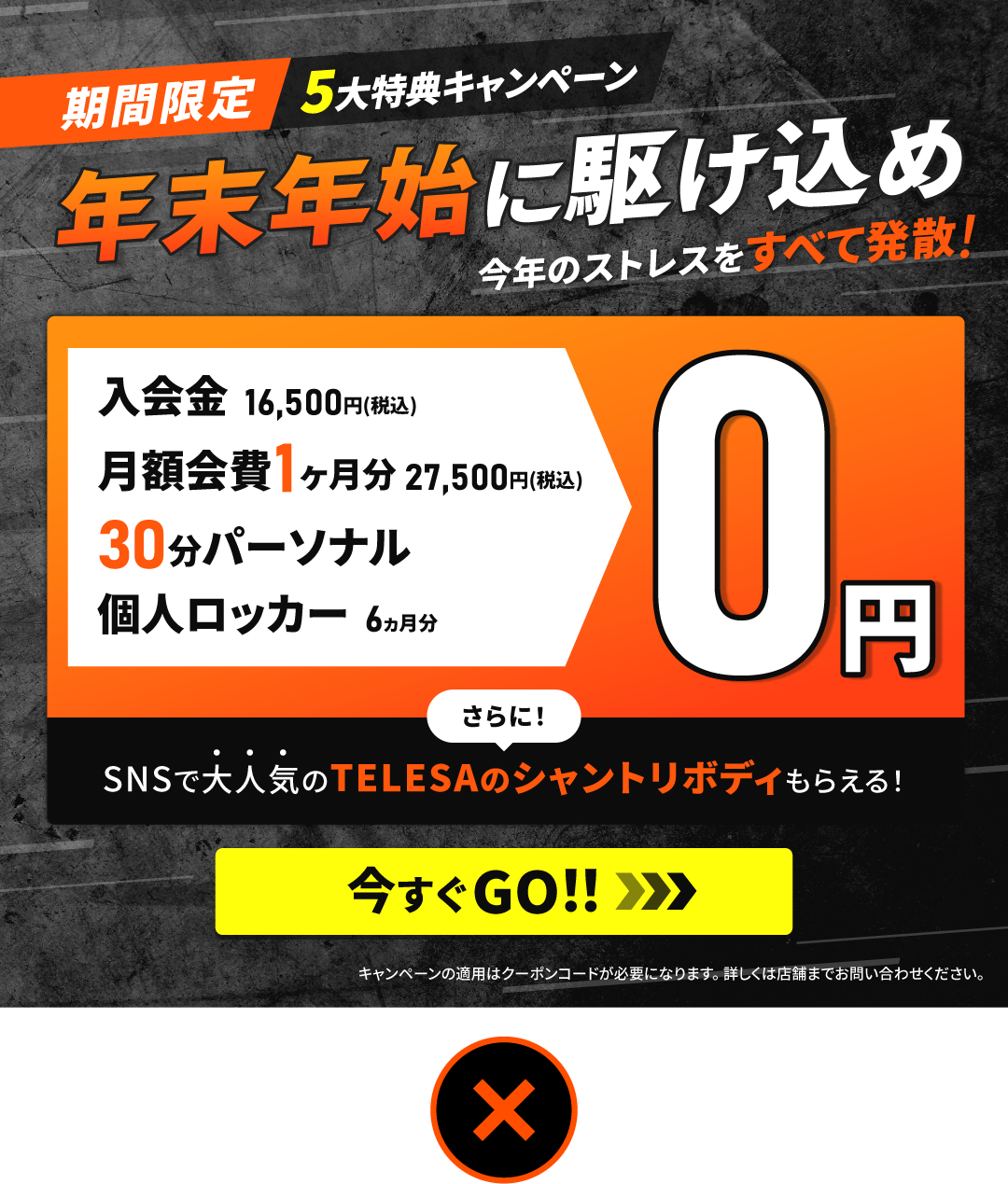ジム用のゴムマット、何を基準に選べば良いか迷っていませんか?
「器具の重みで床がへこまないか」「マンションでも使える防音性能はあるのか」「ゴムの臭いが気にならないか」など、マット選びには想像以上に多くの悩みがつきまといます。特にホームジムの設置を検討している方にとって、マット選びの失敗はそのまま高額な損失や近隣トラブルに繋がることも珍しくありません。
この記事では、ジム用ゴムマットの選び方から設置方法、失敗例、素材ごとの違いまでを徹底解説します。防振・防音対策の重要性や、賃貸住宅での使用時に注意すべき点まで網羅しているので、最後まで読むことで「自宅に最適なマット選びの正解」が見つかります。
専門家監修のもと、最新の業界データと実践に基づいた内容を盛り込んでいます。損をしないためにも、マット選びの前にまずは正しい知識を手に入れてください。

ジム用ゴムマットとは?なぜジムに敷くべきなのか
ゴムマットの基本機能
ジムにおけるゴムマットの役割は、単なる敷物ではなく、トレーニング環境の安全性と快適性を支える基盤として機能しています。ゴムマットの最大の利点は、強力な防音性と衝撃吸収力です。器具を落とした際の床や下階への衝撃を緩和し、騒音を効果的に軽減します。また、防振性に優れているため、トレーニング中の振動によるストレスや不快感も軽減され、集中力を維持しやすくなります。
さらに、床材を傷つけないための保護材としての役割も重要です。特に、重量級のマシンやダンベルを使用する環境では、床面の耐久性が求められます。ゴムチップやラバー素材で作られたマットは、床への直接の衝撃を抑え、表面の摩耗や変色、凹みの発生を防ぎます。また、器具の設置面が安定することで、トレーニング中の事故防止にもつながります。
滑り止め効果も、ジムマットに求められる基本機能の一つです。特に汗や湿気の影響で床が滑りやすくなる環境では、裏面加工によるグリップ性や表面の摩擦特性が重要です。設置場所に応じて、ジョイントタイプや一枚ものの大型マットを選ぶことで、より高い安定性を確保できます。
見た目の美観も忘れてはならない要素です。カラーやサイズの選択肢が豊富なゴムマットを用いれば、ジム全体の統一感が生まれ、利用者にとって居心地の良い空間を演出できます。施設ごとに用途や雰囲気に合わせて選べる点も、導入の魅力です。
以下は、ジムマットに備わる主な機能をまとめた一覧です。
| 機能名 | 役割・特徴 |
| 防音性 | 器具落下時の騒音を軽減し、近隣への影響を抑える |
| 衝撃吸収 | マシンや人の重みを受け止めて床へのダメージを防止 |
| 防振性能 | トレーニング時の振動を吸収し、ストレスや不快感を軽減 |
| 滑り止め | 汗や湿気でも滑りにくく、安全なトレーニングを実現 |
| 床保護 | フローリングやコンクリート面を傷から守る |
| 視覚効果 | 色・形・配置によりジム全体のデザイン性と統一感を高める |
| 設置自由度 | ジョイント・ラバー・ゴムチップなど、形状や厚みに応じて選べる |
このように、ゴムマットはジムにおける多機能なインフラとして不可欠な存在です。利用者の快適性を支えるだけでなく、設備の保全、事故防止、空間演出といった面でも、大きな役割を果たしています。
自宅と施設で異なるゴムマットの必要性
ジムマットの使用目的は「床を保護する」だけにとどまりません。ホームジムと業務用ジムでは、求められる性能や設置環境に大きな違いがあります。まず、施設用のジムマットは大勢が同時に使用することを想定し、高耐久性と衝撃分散性を重視して設計されています。重量器具が繰り返し設置・移動されても耐えられる素材や、通気性・防臭性が加味された構造が採用される傾向があります。
一方、ホームジムでは省スペース・費用対効果・簡易施工が重視されます。特に賃貸住宅やマンションなど、床の傷や騒音への配慮が必要なケースでは、柔らかい素材やジョイントマットが人気です。使用頻度や設置スペースに応じて、最適なマットを選ぶことで快適なトレーニング環境が整います。
また、住宅用では下階への防音性も重要な要素です。マットの厚さが10mm以上になると、足音やダンベルの振動が軽減され、近隣トラブルのリスクも抑えられます。階下に人がいる環境では、素材と設置方法の選択が非常に重要です。
マット選びにおける違いを簡潔にまとめると以下のようになります。
| 項目 | ホームジム | 業務用ジム |
| 使用目的 | トレーニングスペースの確保・床保護 | 多人数対応・高耐久性・連続使用 |
| マットの厚み・素材 | 薄型EVA、ジョイントマットが主流 | ゴムチップ、ラバー素材が中心 |
| 防音・防振対策 | 下階対策として必須 | 高重量器具への耐性と振動吸収が重要 |
| 設置スペース | 限られた面積にフィット | 広範囲かつ均一な敷設が求められる |
| 設置・撤去の容易さ | DIY設置が可能 | 専門施工や接着を伴うこともある |
このように、環境や目的によって選ぶべきゴムマットは異なります。自宅用は簡便さと静音性、施設用は耐久性と機能性を重視することで、最適なパフォーマンスが得られるのです。
ホームジムにおすすめのゴムマット選びと設置の基本
ホームジムマットの選び方
ホームジムにおけるマット選びは、快適なトレーニング環境と安全性を両立させるための重要なポイントです。設置場所の広さやトレーニング内容に応じて、厚み・素材・サイズを的確に選ぶ必要があります。特に、ゴムマットは耐久性・防音性・安定感に優れており、多くのホームトレーナーに選ばれています。
マットの厚みは、トレーニングの種類によって最適な数値が変わります。一般的には10mm前後が標準とされており、ダンベルなどの器具を使用する場合は20mm以上の厚みが推奨されます。マットが厚すぎると安定感を損なうことがあるため、バランスの取れた厚み選定が必要です。
素材については、代表的なものとしてEVA、ゴムチップ、ラバーの3種類があります。EVAは軽量で柔軟性があり、初心者や軽度のトレーニングに適しています。一方、ゴムチップマットやラバー素材は、より強靭な耐久性を持ち、器具の落下など衝撃が加わるトレーニングに向いています。表面が滑りにくい仕様のものを選ぶことで、安全性がさらに高まります。
また、サイズも非常に重要です。設置場所の床面積に合わせて、必要な枚数を計算し、部屋の隅までマットが行き渡るように設計することが求められます。市販されているマットには1枚ごとに規定のサイズがあるため、ジョイントタイプなど組み合わせがしやすいタイプを選ぶと便利です。
以下に、ホームジムに適したマットの選定基準をまとめました。
| 項目 | 選定の目安 |
| 厚み | 軽い運動:10mm前後、器具使用:20mm以上が推奨 |
| 素材 | EVA:軽量・柔軟/ゴムチップ:防音性高/ラバー:耐久性重視 |
| サイズ | 使用範囲に合わせて計算。ジョイント式で自由に調整可能 |
| 表面仕様 | 滑り止め加工・防汚仕様など、安全性と手入れしやすさを確認 |
| 配色 | 室内インテリアに馴染むカラーを選ぶと違和感が出にくい |
このように、マット選びでは単に価格だけでなく、「設置環境に適した厚み・素材・サイズ」をバランス良く見極めることが、快適かつ安全なホームジム作りに欠かせません。購入前には実際の利用シーンを想定し、求める性能と使用スペースを丁寧に整理することが理想です。
床補強は必要か?よくある疑問に答えます
ホームジムにおいて多くの人が直面するのが「床補強は必要か」という疑問です。結論からいえば、設置場所の構造や使用する器具によって異なります。全ての家庭で床補強が必要なわけではありませんが、場合によっては安全面や建物への負担を考慮し、一定の対策が求められることもあります。
まず考えるべきは、建物の構造です。木造住宅や築年数の経過した建物では、重量級のマシンを設置することで床のたわみや沈み込みが発生することがあります。床材や根太の状態が十分でない場合には、荷重が一点に集中しないように、マットによる荷重分散が有効です。
また、コンクリート床であっても衝撃や振動は建物全体に伝わる可能性があります。トレーニング中に器具を落とす行為は、短時間でも大きなエネルギーが床に加わり、階下への振動伝達や音の問題に発展するケースがあります。これを防ぐためにも、防音・防振性能のあるゴムマットの使用が望ましいです。
「ホームジム 床補強 必要 ない」という検索ニーズがある一方で、使用器具や部屋の構造によっては、やはり注意が必要です。特に以下のようなケースでは、床補強や工夫が推奨されます。
- バーベル・スミスマシンなど重量器具を設置予定
- トレーニング時にダンベルを落とす頻度が高い
- 床に微細なヒビや凹みがすでにある
- 階下が生活スペースになっている集合住宅
上記のような状況であれば、床の補強を「する・しない」の判断材料として以下のように整理するとわかりやすくなります。
| 判断項目 | 補強の必要性目安 |
| 建物構造 | 木造住宅:必要な可能性あり |
| 器具の重量 | 軽量器具:不要/重量級:対策推奨 |
| 設置フロア | 1階:不要/2階以上:対策必要 |
| 階下の使用状況 | 居住空間:防振・防音対策が有効 |
| 既存床の状態 | ひび割れや沈み込みがある場合は要確認 |
このように床補強の要否は、単純に「必要か否か」では判断できません。設置環境と器具の種類を踏まえ、ゴムマットや緩衝材などを効果的に使うことで、不要な工事を避けつつ、安全性を高める選択肢もあります。
ゴムマットの種類を徹底比較
ジョイントマット vs ゴムチップマットの違い
ジムやホームジムに敷かれるゴムマットの中でも、特に人気があるのがジョイントマットとゴムチップマットです。どちらも床を保護し、トレーニング環境を整える役割を果たしますが、特徴や用途は大きく異なります。ここでは、それぞれの違いを深く掘り下げながら、どんな場面でどちらを選ぶべきかを明確にしていきます。
ジョイントマットは、パズルのように組み合わせて使用できるタイプで、主にEVA素材やポリエチレン系の柔らかい素材でできています。軽量で扱いやすく、設置や撤去が簡単なため、家庭での筋トレやストレッチマットとして活用されています。厚さは10mm前後が多く、カラーやサイズも豊富に揃っており、インテリア性を損なわずに導入できます。
一方、ゴムチップマットは、リサイクルゴムや天然ゴムを粉砕し、成型加工したものです。重量があり、床にしっかり密着するためズレにくく、重い器具を使うトレーニングにも対応可能です。防振・防音・衝撃吸収性に優れ、商業用ジムや重量トレーニング向けに重宝されます。耐久性が高く、表面の摩耗にも強いため、長期間の使用にも適しています。
以下に、両者の違いを整理した表を示します。
| 項目 | ジョイントマット | ゴムチップマット |
| 主な素材 | EVA、ポリエチレンなど | リサイクルゴム、天然ゴム |
| 重量 | 軽量 | 重量あり |
| 防音・防振性 | やや弱い | 非常に高い |
| 耐久性 | 中程度 | 高い |
| 施工のしやすさ | 簡単(カット可能、接着不要) | やや手間(カットに工具が必要) |
| 滑りにくさ | 表面加工で対応(製品により異なる) | 高い(凹凸がありしっかりグリップ) |
| 用途 | 軽い筋トレ・ストレッチ・家庭用 | 本格的な筋トレ・商業施設・重量器具下敷きに最適 |
ジョイントマットは、スペースに合わせて柔軟に調整できるため、初めてホームジムを作る方にも適しています。一方で、本格的な器具を導入したい、あるいは重量器具を使う予定がある場合は、ゴムチップマットの導入が適しているといえるでしょう。
設置場所の床材や、トレーニング内容、想定される衝撃の大きさを総合的に判断し、マットの種類を選ぶことが重要です。
EPDMやラバー素材の性能とは?
ゴムマットの素材として注目されているのが、EPDMと呼ばれる合成ゴムやラバー素材です。これらは、ジムマットやフロアマットなどの製品でよく使用されており、耐久性や防水性、耐候性などに優れている点が特徴です。ここではEPDMとその他ラバー素材の性能に焦点をあて、ホームジムや業務用ジムにおける適性を解説します。
EPDMはエチレン・プロピレン・ジエン系の合成ゴムで、工業用・建材用としても広く利用されています。特に、屋外環境での耐紫外線性や耐熱性に強く、変色や劣化が起きにくいのが利点です。また、摩耗にも強いため、設置後も表面が削れにくく、ジムマットとして高い耐久性を発揮します。
ラバー素材全般としては、天然ゴムをはじめ、リサイクルゴムを使用したゴムフロアマットやゴムチップマットなどが該当します。EPDMよりも柔軟性や弾力に富んだタイプもあり、防振・防音性能に優れたマットを探しているユーザーに支持されています。
以下に、EPDMとその他ラバー素材の比較を整理した表を掲載します。
| 特性項目 | EPDM素材の特徴 | ラバー素材(一般)の特徴 |
| 耐候性 | 非常に高い(屋外でも劣化しにくい) | 通常程度(屋内使用に適する) |
| 耐熱性 | 高温下でも変形しにくい | 標準的(長時間の直射日光は避ける) |
| 防水性能 | 優れている(水や湿気に強い) | 高め(表面加工により差がある) |
| 防音・防振 | 製品によるが高性能タイプが多い | 高性能(特にゴムチップマットは優秀) |
| 環境適応性 | 屋内外を問わず使用可能 | 主に屋内使用が前提 |
| 価格帯 | 高価格帯 | 中〜低価格帯 |
| カラー展開 | グレー・ブラックが主流 | ブラック中心だがカラーチップ付きも多い |
EPDMは「長期使用に耐える」「屋外環境にも対応できる」「紫外線や温度変化に強い」という点で、設置場所を選ばない万能素材としての評価が高まっています。一方で、価格はやや高めに設定されているため、費用を抑えたい場合や室内使用限定であれば、スタンダードなラバー素材の製品が現実的です。
素材の違いはトレーニングの質や安全性に直結するため、見た目や価格だけでなく、使用頻度・設置環境・求める性能を総合的に考慮した選定が必要です。
ゴムマットの厚みとサイズ選びガイド
ジム用途別に見る最適な厚みとサイズ
ホームジムやトレーニングジムでの使用を前提としたゴムマットは、使用目的や設置スペースにより選ぶべき厚みとサイズが異なります。例えば筋トレ用としてバーベルやダンベルを扱うスペースでは、強い衝撃を吸収するために厚手のマットが望ましい一方、ヨガやストレッチを中心としたエリアでは、薄手でも十分なケースがあります。
ジムで用いられる主なゴムマットの厚みは、10mm、15mm、20mm、30mm、40mmなどが一般的です。厚みごとの特徴を把握することで、安全性や使用感が大きく変わるため、適切な選択が重要になります。
以下に、厚みと用途の関係を簡潔にまとめます。
| 厚みの目安 | 主な用途 | 特徴 | 吸音性 | 衝撃吸収性 |
| 10mm以下 | ヨガ・ストレッチ | 軽量・手軽 | 弱い | 弱い |
| 15mm | 自重トレーニング | 基本的な防音と防振を兼ねる | 中程度 | 中程度 |
| 20mm以上 | ダンベル・バーベル使用エリア | 衝撃吸収性に優れる | 高い | 高い |
| 30mm〜40mm | 業務用ジム・商用施設 | 高強度の運動にも対応 | 非常に高い | 非常に高い |
また、マットのサイズも重要な選定要素です。マットは一般的に60cm角、90cm角、100cm角などのジョイントタイプや1m×1m以上のゴムチップマットなどが流通しています。サイズ選びは設置スペースに合わせるのはもちろん、重量器具の配置や移動のしやすさ、カットのしやすさも意識する必要があります。
さらに、ジョイントマットの場合は縁に凹凸があるため、隙間のない設置が可能となり、見た目の一体感や安全性も向上します。逆に1枚もののラバーマットは耐久性に優れる反面、重さや加工のしにくさに留意すべきです。
選定時には、以下のような条件で比較検討してみてください。
・トレーニング器具の重量と衝撃度合い
・設置スペースの広さと形状
・騒音対策(下階への配慮)
・メンテナンス性(掃除・交換)
・費用対効果(価格帯とのバランス)
ジムで安全かつ快適なトレーニング空間を実現するためには、単に厚みがあれば良いというものではなく、用途に応じた厚みとサイズの適切なバランスが鍵を握ります。特にホームジムでは、床の補強と合わせて最適なマット選びが必要となるため、商品レビューや実際の使用者の声も参考にすることが有効です。
床の凹凸・傾斜がある場合の敷設方法
ジムマットを設置する際、意外と見落とされがちなのが「床の状態」です。特に住宅の一室を活用したホームジムでは、床に微妙な傾斜や凹凸が存在することがあります。これを放置してマットを敷いてしまうと、マシンや器具の安定性が損なわれ、トレーニング中の安全性に悪影響を及ぼす恐れがあります。
床の凹凸や傾斜がある場合の対処法として、まず「現状の床状態をチェックする」ことが重要です。水平器を使って床の傾きや段差の有無を確認し、段差が目立つ場合は以下の方法を検討する必要があります。
- 薄手の下地材(ベニヤ板やゴムシート)で段差を補正する
- 凹凸部分にあわせてマットの厚みを変える
- 特殊な防振ゴムを併用し、安定性を確保する
また、ジョイントマットを使用する場合には、マット同士が浮いたりズレたりしやすくなるため、床が完全に平らでない環境では、1枚もののマットを選ぶか、ジョイント部分に専用の連結部材(コネクタ)を活用するのが効果的です。
傾斜が緩やかな場合でも、マシンの滑りを防ぐために「滑り止め加工」が施されたゴムマットや「裏面に吸着構造があるタイプ」を選ぶことで、設置後のズレや動きを抑えることができます。
次に、設置後のマットが浮いてしまったり、マシンの脚部分だけが沈み込むような事象を避けるためにも、ゴムマットの厚みによる補正が求められます。たとえば、傾斜があるスペースでは部分的に20mmから30mmの厚さを調整しながら敷設することで、床全体をできるだけ水平に近づけることが可能です。
また、傾斜や凹凸のある床にラバー系マットを敷く場合、耐久性や復元力の高いEPDMやSBR素材を使った製品を選ぶと、長期間にわたって歪みにくく快適に使用できます。
このように、ゴムマットの敷設では「床の状態に応じた工夫」が安全性と快適性に直結するため、設置前のチェックと対処は決して省略できない重要な工程といえるでしょう。
ゴムマットの臭い対策とメンテナンスのコツ
新品マットのゴム臭の原因と安全性
新品のゴムマットから発生する独特な臭いは、多くの利用者にとって気になる要素の一つです。この臭いの主な原因は、ゴム素材自体に含まれる揮発性有機化合物(VOC)です。これらはゴムの製造過程で使用される添加剤や加硫剤、染料などが揮発することで生じるもので、特に設置直後のマットや高温多湿の環境下では顕著に感じられます。
この臭いが健康に悪影響を及ぼすかどうかに関しては、一般的に家庭用・業務用のゴムマットに使用されている素材は、安全基準を満たしているものが多く、短時間の使用では健康への重大な影響はないとされています。ただし、敏感な人や小さな子ども、高齢者が利用する空間では、設置前後の換気が重要です。
特にホームジムやトレーニングルームなど、長時間滞在する場所にマットを敷く場合は、事前に臭い対策を講じることで快適性を高められます。製造元が日本のブランドである製品は、比較的臭いが少ない傾向にあり、設置後のトラブルを未然に防ぐ選択肢となります。
以下は、ゴムマットの臭いの原因と発生状況の比較です。
| 要因 | 詳細内容 |
| 素材 | ゴムチップ、ラバー、EPDMなどで臭いの強さに差がある |
| 製造方法 | リサイクルゴム使用か新品ゴム使用かで差がある |
| 揮発成分 | VOC(揮発性有機化合物)の種類や量による |
| 温度・湿度 | 高温・多湿環境では臭いが強くなる傾向 |
| 保管状態 | 密封状態で長期保管された製品は臭いがこもりやすい |
臭いの感じ方には個人差があるため、一概にすべてのユーザーに影響があるとは限りません。しかし、快適なトレーニング環境づくりを目指す上で、素材選びと設置前の下処理は非常に重要なポイントといえるでしょう。
臭いを軽減する具体的な対処法
ゴムマットの臭いを抑えるための方法は複数存在しますが、いずれも科学的根拠や実用性に基づいた対処が求められます。臭いの強さや使用環境に応じて、対策を組み合わせることが最も効果的です。
まず有効なのは、設置前の「屋外換気処理」です。マットを開封した状態で風通しの良い屋外またはベランダに1~2日ほど置くことで、初期臭をかなり軽減できます。この段階で表面に付着した油分や化学成分が蒸発しやすくなります。
次に推奨されるのは「拭き取り洗浄」です。中性洗剤を水で薄めた溶液を用い、マイクロファイバークロスなどで優しく拭くことで、表面のにおい成分を減らす効果が期待できます。この工程は特にリサイクルゴムを使用しているマットで効果が大きいです。
さらに、「活性炭シートや脱臭スプレーの併用」もおすすめです。ただし、香料を含むスプレーは素材を劣化させるリスクがあるため、無香料かつゴム対応の製品を選ぶことがポイントです。
以下に、臭い軽減策の実用性を比較した表を掲載します。
| 対処法 | 効果の目安 | メリット | 注意点 |
| 屋外干し | 中〜高 | 揮発成分を自然に飛ばせる | 雨や直射日光に注意 |
| 中性洗剤で拭く | 中 | 表面の化学成分を除去可能 | 強く擦らないこと |
| 活性炭設置 | 中 | 空間全体の臭いに効果 | 定期的な交換が必要 |
| 無香料スプレー | 低〜中 | 即効性がある | 材質によっては変色リスクあり |
| 換気の徹底 | 中〜高 | 全体的な臭気対策に有効 | 設置後も定期的な換気が必要 |
こうした対策は、新品マットだけでなく、長期間使用したマットにも有効です。設置後に時間が経ってから臭いが気になり始めるケースもあるため、継続的なメンテナンスが快適な室内環境維持には不可欠です。
ゴムマットの設置方法と注意点
事前準備と設置スペースの確認ポイント
ゴムマットの設置をスムーズに進めるには、設置前の準備と空間確認がとても重要です。特にホームジムやトレーニングスペースにゴムマットを導入する際には、床の状態、マットの厚み、設置スペースの形状やサイズを把握することが、仕上がりや安全性を大きく左右します。
まずはスペースの測定から始めます。一般的なホームジムでは、ダンベルやマシンなどの器具を置くため、設置面積は最低でも約2畳(約180cm×180cm)を目安に確保するのが無難です。加えて、器具の重量や移動の動線を考慮して、壁際にゆとりをもたせた配置が推奨されます。
次にマットの厚みの検討です。以下のように目的に応じた厚みの選定が必要です。
| 用途 | 推奨厚み | 理由 |
| ストレッチ・軽運動 | 約5mm | クッション性があり、設置・撤去も手軽 |
| ダンベル使用時 | 約10mm | 衝撃吸収に優れ、床保護と騒音対策に効果的 |
| バーベル・マシン使用 | 15mm以上 | 強靭なゴムチップマットが必須。耐荷重性と安定性が必要 |
設置場所の床材質もチェックしましょう。フローリングやクッションフロアなどは、ゴムマットとの相性によって滑りやすさやカビ発生リスクに差が出ます。滑りを防ぐためには裏面に凹凸やラバー加工がある製品が適しています。
さらに、ゴムマットの設置には室温・湿度も影響します。寒冷地や梅雨時期など湿気がこもりやすい環境では、ゴムの収縮・膨張が生じやすいため、設置前に数時間マットを広げて馴染ませることが推奨されます。
加えて、以下の項目も準備段階で確認しておくことが重要です。
- 使用する器具の重量と床耐荷重
- 賃貸物件かどうか(防音や傷対策)
- 設置後のメンテナンススペースの確保
- マットの配送形態と梱包材の処分方法
- 屋外や地下スペースなど特殊環境下での適応性
これらの準備を丁寧に行うことで、設置後のトラブルを未然に防げます。初めての設置であっても、計画性と事前確認を意識することで、安全で快適なトレーニングスペースの土台づくりが実現できます。
施工時の注意点とよくある失敗例
ゴムマットを設置する際には、見た目の美しさだけでなく、耐久性や安全性を保つための細やかな配慮が求められます。特にジョイントタイプやロールタイプのマットを使用する場合には、施工方法を誤ると隙間や浮き、ズレの原因になり、長期間の使用に支障をきたす恐れがあります。
まず失敗しがちなポイントとして「接地面の不均一」が挙げられます。微細な凹凸やホコリ、床の歪みがある状態でマットを敷くと、滑りやすくなりマットの寿命も短くなります。施工前には必ず掃除と水拭き、乾燥を徹底し、床全体の状態をフラットに整えることが重要です。
次に「ジョイントのズレや浮き上がり」。ジョイントマットを組み合わせる場合、組み合わせ方向が揃っていないと段差が生まれやすくなります。すべて同一方向でジョイントするだけでなく、圧力を均等にかけながら組み込むことで密着度が向上します。
以下は、よくある施工ミスとその回避策です。
| よくあるミス | 原因 | 回避方法 |
| マットが波打つ・反り返る | 温度変化や設置直後の未定着 | 設置前に室温に慣らす・重しをのせて定着させる |
| 隙間が空く | ジョイント方向の不一致・サイズ誤差 | カット前に全体を仮配置し、正確に測定して調整する |
| 端がめくれる | 粘着不足・マットの反り返り | 両面テープや滑り止めパッドの使用が効果的 |
| においがこもる | 換気不足 | 設置中・設置後にしっかり換気し密閉を避ける |
| 床を傷つける | 床材との相性が悪い | 保護シートや緩衝マットを併用して床材を守る |
また、設置に時間がかかるケースもあります。広い面積や複数階への敷設の場合、作業が半日以上になることも想定しておきましょう。作業時間を短縮するには2人以上で分担するのが効果的です。
専門業者による施工も選択肢のひとつです。特に業務用ジムや大型器具を扱う場合は、施工保証や技術的ノウハウのある業者の導入で長期的なトラブルを防げます。
見た目の整った敷設はモチベーションにも直結します。作業中は必ず水平器やメジャーを活用して均一性を保つことを心がけましょう。
まとめ
ジム用ゴムマットは、単なる床の保護材ではありません。防音や衝撃吸収といった機能面に加え、設置環境や使用器具に応じた適切な厚みや素材の選定が、トレーニング効率と安全性を大きく左右します。
たとえば重量級の筋トレ器具を扱う環境では、ゴムチップマットや2.5cm以上の厚さを持つ業務用仕様が求められます。一方、賃貸や集合住宅での設置には、防振性と防臭性に優れたEPDM系マットが重宝されており、裏面加工によって床材への影響も最小限に抑えられます。
また、施工時の失敗例として多いのが、床の凹凸や通気性を無視した敷設によるカビの発生。特に湿度が高い日本の住宅環境では、敷設前の事前準備とメンテナンス体制がカギになります。
この記事では、専門家監修のもと、現場経験に基づいた選び方から設置・管理までを網羅的に解説しました。ゴムマット選びは一度の判断で長期的な満足度を左右するため、曖昧な選択は避けたいところです。
安心してトレーニングに集中できる空間を手に入れるために、今こそ知識と準備が求められています。あなたのホームジムを後悔のない形に仕上げるため、この記事の情報をぜひ活用してください。

よくある質問
Q. ゴムマットの臭いが心配です。対策や無臭の製品はありますか?
A. 新品のゴムマットに特有の臭いは、主に加工時のラバー成分とゴムチップ由来の揮発性物質が原因です。24時間以上の換気と風通しの良い場所での陰干し、消臭スプレーによる拭き取りで大幅に軽減されます。最近では無臭加工されたEPDM素材の製品や、食品衛生法に適合した日本製の低臭マットも販売されています。レビューでは特に「ゴム臭がない」と記載された商品が人気を集めており、Amazonなどの通販ショップでも臭い対策済のゴムチップマットの注文が増えています。
Q. 初めてでも失敗しないジム用ゴムマットの設置方法を教えてください
A. 初心者がジム用ゴムマットを設置する際は、まず設置スペースのサイズを正確に測ることが基本です。例えば180cm×120cmのスペースに器具を設置する場合、縦横の凹凸や段差を確認し、ジョイントタイプのマットで対応するのが最も簡単です。施工時には隙間が生まれないようにコネクタやエッジガードを使用し、滑り止めシートや粘着パッドで固定することでズレ防止にもなります。日本の住宅事情に合わせたカット対応や裏面補強付きのゴムマットは特に人気で、設置からメンテナンスまでの工程が簡略化されており、DIY初心者でも対応しやすくなっています。
会社概要
会社名・・・GYM&SAUNA
所在地・・・〒150-0034 東京都渋谷区代官山町20-9 サザン代官山B1F
電話番号・・070-8347-5991