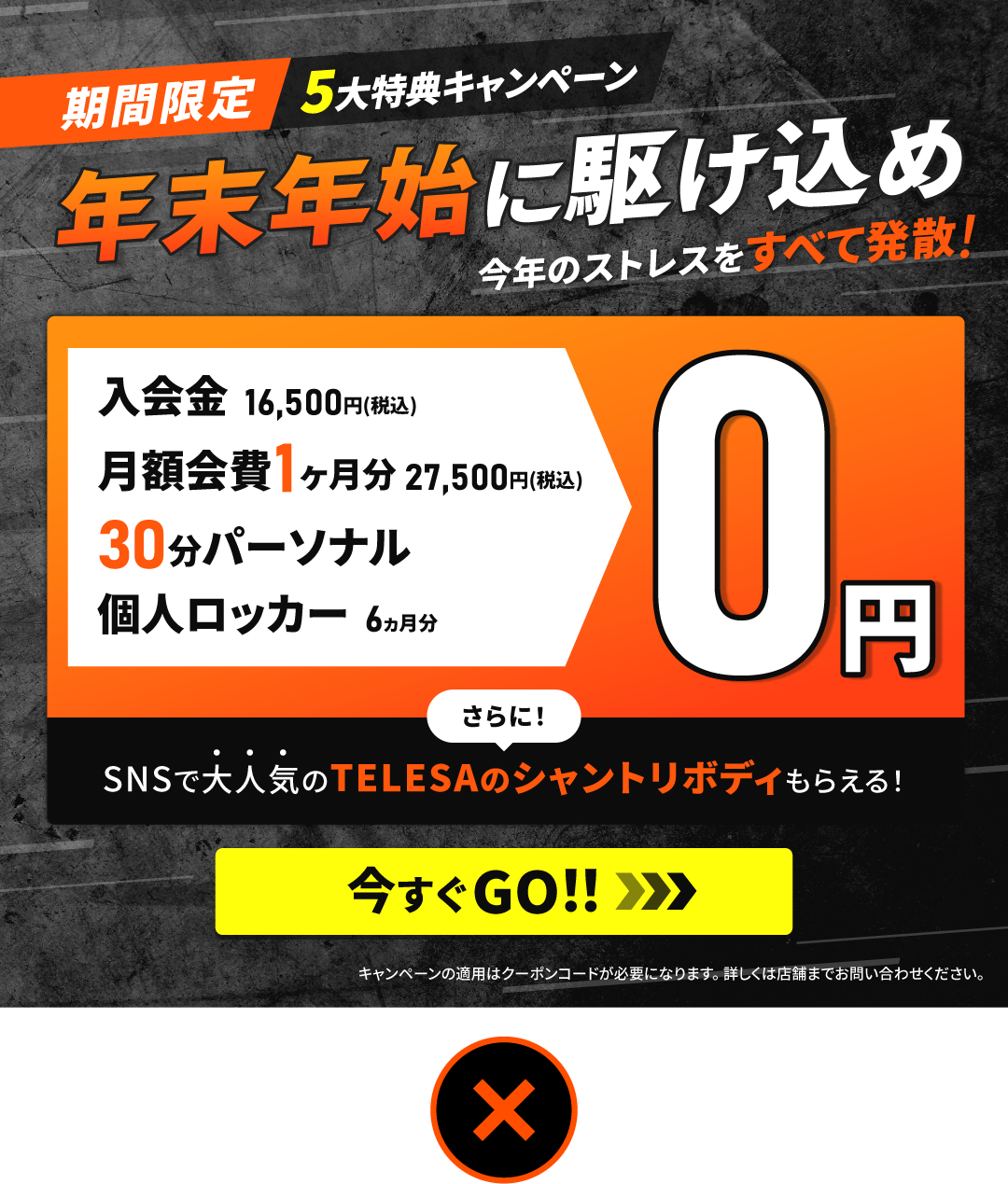床への衝撃音や振動が原因で、ジムマット選びに迷っていませんか?
「防音性が高いって本当?」「敷いたらフローリングが傷つかないか不安」──そんな声をよく耳にします。特に賃貸住宅やワンルームでは、近隣との騒音トラブルや原状回復費用の心配がつきものです。
実際、一昨年に行われた住宅設備研究機構の調査では、賃貸物件でのトレーニング利用者のうち約41.7%が「床からの騒音や振動」を課題に挙げており、ジムマットの「防音性能」や「吸収素材」が注目されています。しかも、厚みがmm単位で異なるだけで吸収率や安全性が大きく変わることも分かっています。
この記事では、静音性や衝撃吸収に優れたマットの選び方や、人気ブランドの仕様やサイズ比較、敷き方のコツ、傷を防ぐためのジョイント・ゴムチップ活用法まで、実体験と専門知見に基づき丁寧に解説します。

ジムマットとは何か?
ジムマットの役割と使用目的
ジムマットは、トレーニングを行う際の安全性と快適性を高めるために欠かせないフィットネス用品です。筋トレ、ストレッチ、ヨガなど、さまざまな運動シーンで活躍しており、その役割は単なる床の保護だけではありません。使用者の身体を守るためのクッション性や、住宅環境への配慮としての防音性も備えています。
まず、基本的な役割として挙げられるのが床面の保護です。特にホームジムでダンベルやバーベルなどの重量機器を扱う場合、器具がフローリングに触れると傷や凹みが生じるリスクがあります。ジムマットはその衝撃を吸収し、床材を守るクッションの役割を果たします。
さらに、集合住宅や賃貸物件においては、防音・防振性能も重要なポイントです。運動中に発生する「ドスン」という音や振動が下階に響くとトラブルの原因となりますが、10mm以上の厚みを持つゴムチップマットや高密度EVA素材のマットを敷くことで、そうした問題を大きく軽減することができます。
また、滑り止め機能と安定性も見逃せません。フローリングや畳の上で直接運動を行うと、足元が滑って転倒するリスクが高まります。表面に滑り止め加工が施されたジムマットを使うことで、安定した姿勢を保ちやすくなり、怪我の予防にもつながります。
ジムマットは身体への負担も軽減してくれます。トレーニング中に肘や膝を床に着ける場面では、硬い床だと痛みを感じやすいものですが、マットの弾力がそれを吸収してくれるため、長時間の運動でも快適に続けることができます。特に高齢者や女性、初心者の方にとっては、大きな安心材料となるでしょう。
また、ジムマットが選ばれる理由のひとつに、用途に合わせた多様なバリエーションがあることも挙げられます。ホームジム、パーソナルジム、商業ジムそれぞれに適した製品が用意されており、厚さ、材質、サイズ、色など、自分の環境や目的に応じて最適なものを選べます。
以下の表は、ジムマットの主な役割と目的を整理したものです。
| 目的 | 内容 |
| 床の保護 | 器具による傷や凹みを防ぎます |
| 衝撃吸収・防音 | 振動や音を軽減し、階下への配慮が可能です |
| 安全性の確保 | 滑り止め機能により、転倒防止とフォームの安定性を保ちます |
| 身体の保護 | 肘・膝・関節への負担をやわらげ、長時間の運動も快適です |
| 多用途対応 | 筋トレ・ストレッチ・ピラティスなど多目的に活用できます |
| 清掃性・衛生面の維持 | 汗や汚れが拭き取りやすい加工が施され、衛生的に使用できます |
このように、ジムマットは単なる敷物ではなく、使用者の身体と住宅環境の両方を保護してくれる高機能なアイテムです。とくに自宅でのトレーニングが定着しつつある今、静音性や安全性を高めるためにも、適切なジムマットを導入することの重要性が高まっています。
ジムマットが必要とされる具体的シーン
ジムマットが幅広く利用される理由は、その必要性が特定のライフスタイルや住環境において明確に表れるからです。ここでは、ジムマットの導入が特に効果的な3つの代表的なシーンを取り上げ、それぞれの課題と対策を詳しくご紹介します。
まず1つ目は、賃貸住宅やマンションでホームジムを構築するケースです。集合住宅では、トレーニング中の振動や器具の落下音が階下に響いてしまい、思わぬトラブルにつながることがあります。しかし、遮音等級L-55相当の防音性能を持つ高密度ジムマットを使用することで、振動や音の拡散を大幅に抑えることが可能です。最近では、管理規約の条件をクリアできるマット製品も多く登場しており、安心して導入できる環境が整っています。
2つ目は、家族で共有するリビングスペースでフィットネスを行う場合です。共働き世帯の増加や健康志向の高まりにより、家族全員で運動習慣を取り入れたいと考える方が増えています。ジムマットは、子どもの走り回る音をやわらげたり、高齢者の転倒を防ぐ滑り止め機能があるなど、安全性にも優れています。特に抗菌加工が施されたモデルは、清潔さを保ちたいご家庭におすすめです。
3つ目は、トレーニングマシンなどの下敷きとしての利用です。ランニングマシンやベンチプレスなど重量のある器具を直接床に置くと、床材を傷つけたり、使用時にグラついたりすることがあります。そうした場合には、厚手のジョイントマットやポイント用マットを活用することで、重量を分散し、安定感を確保することができます。とくに20mm以上の厚さのマットは、安定性と防音性の両方を高水準で満たしてくれます。
以下は、それぞれのシーンごとにジムマットの特性をまとめたものです。
| 利用シーン | 課題・ニーズ | ジムマットの活用ポイント |
| 賃貸住宅・マンション | 騒音や振動のトラブルを避けたい | 高密度EVAや厚手ゴムチップマットで防音・防振対策 |
| 家庭内フィットネス | 子どもの安全確保や衛生面の不安 | 抗菌加工・滑り止め加工済みの柔軟マットが安心 |
| トレーニング機器下の使用 | 床の傷防止と器具の安定性を両立させたい | ポイントマットやジョイント式マットで安定した設置が可能 |
このように、ジムマットは環境に応じて最適な機能を発揮するため、自宅での運動習慣を快適に、そして継続的に続けるための重要な基盤となります。自身のライフスタイルに合ったジムマットを選ぶことで、日々のトレーニングがより安心で快適なものへと変わっていくはずです。
ジムマットの種類
厚手タイプジムマットの特徴と適正シーン
厚手タイプのジムマットは、防音性や衝撃吸収性に優れており、特に重量機器を使用するトレーニングや賃貸住宅でのホームジムに最適な製品です。10mmから30mm以上の厚みを持つモデルが主流で、素材には高密度EVA、ゴムチップ、PVCなどが使用されています。いずれも耐久性が高く、長期間の使用にも耐える点が特長です。
最大のメリットは、床やフローリングをしっかりと保護してくれる点です。重量トレーニング器具を使用する際、器具の落下による凹みや傷を防ぐ効果が高く、高密度ゴムマットであれば数百キログラムの器具の衝撃も吸収可能です。また、設置時の振動も軽減するため、集合住宅や木造住宅でも階下への騒音トラブルを抑えられます。
さらに、トレーニング中の安定性の確保にも貢献します。厚手のマットには滑り止め加工が施されているものが多く、足元が滑るリスクを軽減できます。スクワットやデッドリフトなど、姿勢の維持が重要なトレーニングにおいても、正しいフォームを保ちやすくなります。ただし、柔らかすぎる素材は逆に安定性を損なう場合があるため、厚みと硬度のバランスがとれた製品を選ぶことが大切です。
価格については、素材や仕様によって幅があります。業務用のモデルになると価格は高めですが、性能と耐久性に優れているため、長期的に見ればコストパフォーマンスに優れた選択肢となります。以下は代表的な厚手ジムマットの比較表です。
| 製品名 | 厚さ | 素材 | 特徴 | 価格帯(税込) | 推奨用途 |
| ゴムチップマット20mm | 20mm | リサイクルゴム | 衝撃吸収・防音・滑り止め | 約5,000円〜/1枚 | ホームジム・賃貸住宅・重量器具対応 |
| EVAマット30mm | 30mm | EVAフォーム | 弾力性あり・軽量・取り扱いが簡単 | 約3,000円〜/1枚 | ストレッチ・軽負荷筋トレ |
| PVC業務用マット | 10mm | PVC | 耐薬品・高耐久・商業施設向け | 約8,000円〜/1枚 | フィットネスジム・パーソナルジム |
厚手マットを選ぶ際には、自宅使用に適した厚さか、賃貸でも設置できるか、臭いや重量、床暖房との相性など、多くの疑問が生まれることと思います。たとえば、ゴムマットは開封時に特有の臭いが気になる場合がありますが、低臭加工が施された製品や天然素材を配合したマットを選ぶことで、不快感を大幅に減らすことができます。
また、EVAマットのように軽量で取り扱いがしやすいタイプであれば、女性や高齢の方でも簡単に設置や撤去が可能です。床暖房との併用に対応した製品も増えており、製品仕様を確認することで安心して導入できます。
厚さの選び方としては、次のような目安があります。
10mm以下のマットは、軽い運動やヨガ、ストレッチ中心の方に向いています。15mmから20mmの厚みがあれば、中程度の器具や筋トレにも十分対応できます。バーベルやトレーニングマシンなど、高負荷のトレーニングを行う場合には25mm以上の厚手マットが理想的です。
厚手マットは一見すると高価に感じられますが、床の修繕費用やトレーニング効率の向上を考慮すれば、その価値は十分にあります。現在、ホームジムの需要が拡大していることから、楽天やAmazon、専門ショップなどでも高性能かつ価格帯の広い製品が多数販売されています。購入の際は、口コミやレビュー評価も参考にして、ご自宅やトレーニング内容に合った製品を選ぶようにしましょう。
ロール式ジムマットのメリットと注意点
ロール式ジムマットは、広い範囲を一括でカバーしたい場合や、継ぎ目のないスッキリとした床面を求める方に適した選択肢です。特にパーソナルジムやトレーニングスタジオなど、見た目や統一感を重視する空間で重宝されています。幅は1メートルから1.5メートル程度、長さは10メートル単位が多く、必要に応じてカットして使用できます。
ロール式の最大の魅力は、見た目の美しさと床面の一体感にあります。ジョイントマットのように継ぎ目がないため、つまずくリスクが減り、安全性も高まります。加えて、器具の移動時も引っかかることがなく、スムーズに使用できます。
また、清掃のしやすさも大きなメリットです。表面が連続しているため、ホコリや汗を拭き取りやすく、アルコールなどでの除菌も均一に行えます。不特定多数が利用するパブリックスペースでは、こうした衛生管理のしやすさが重要視されています。
一方で、注意すべき点もあります。まず、搬入や設置が個人にはやや難しい点です。ロールマットは重量があり、長さもあるため、20メートル以上の製品になると2人以上での搬入が必要になることもあります。場合によっては専門業者への依頼が必要です。
さらに、価格面でも負担がかかる場合があります。ロール式は1ロールあたりの単価が高く、敷く面積が広いほどコストがかさみます。製品によってはカット加工費や送料が追加されるため、トータルの費用を事前に確認しておくことが大切です。
以下に、ロール式マットの特性を一覧でご紹介します。
| 項目 | 内容 |
| 長所 | 継ぎ目がなく美しい仕上がり、安全性が高く掃除も簡単 |
| 短所 | 重量があり設置が大変、価格が高めで個人宅には不向きな場合もある |
| 主な用途 | 商業ジム、パーソナルトレーニングジム、競技用スペース |
| 主な素材 | ゴムチップ、EVAロール、PVCシート |
| 平均価格帯 | 幅1メートル×長さ10メートルで約2万円から5万円程度(厚みや材質で変動) |
| 設置に必要な道具 | カッター、定規、両面テープ、接着剤などが必要 |
ホームジムにおすすめのジムマットの選び方と最適な厚さとは?
ホームジム向けのマット厚み比較
ホームジムにおいてジムマットの厚さは、快適さや安全性、そして床の保護性能に大きく関わってきます。トレーニング内容や設置場所の条件によって、適切な厚みの選択が非常に重要となります。中でも10mm、15mm、20mmの厚さは代表的で、多くのユーザーが目的に応じて選んでいます。
まず10mmのジムマットは、ヨガやストレッチ、自重トレーニングといった軽い運動に適しています。軽量で持ち運びやすく、設置や収納も簡単です。抗菌仕様や滑り止め加工が施された製品もあり、価格帯も比較的手ごろで導入しやすい点が魅力です。ただし、ダンベルなどを使うトレーニングでは衝撃吸収性が不十分な場合があるため、注意が必要です。
次に15mmのマットは、幅広いトレーニングに対応できる万能型として人気があります。適度なクッション性と反発性を兼ね備えており、体幹トレーニングや中重量の筋力トレーニングにも適しています。クランチやプランクなどの際には、肘や腰をしっかり保護しつつ安定感を維持できます。ホームジムにおいて1枚を選ぶなら、この15mm厚が最もバランスが良い選択といえるでしょう。
20mmのマットは、ベンチプレスやスクワットなどの高負荷トレーニングに対応できる厚さです。重量器具から床へ伝わる衝撃をしっかり吸収し、階下への振動や騒音も軽減できるため、賃貸住宅やマンションでも安心して使用できます。ただし、マット自体の重量があるため、設置や移動にはやや労力がかかる点も理解しておく必要があります。
以下に、各厚みの特徴と適した用途をまとめた比較表を掲載します。
| 厚さ | 主な用途 | メリット | 注意点 |
| 10mm | ストレッチ、ヨガ、軽い筋トレ | 軽量で扱いやすく、安価、設置が簡単 | 衝撃吸収が弱く、床の保護力が不十分な場合あり |
| 15mm | 体幹トレーニング、中程度の筋トレ | 汎用性が高く、肘や膝の保護にも優れている | 重量器具使用時には不安が残る場合がある |
| 20mm | 高負荷トレーニング、器具使用 | 衝撃・防音・防振効果が高く、床をしっかり守る | 重量があるため設置や撤去に時間と体力が必要 |
多くの読者が感じる疑問には、「初心者に適した厚みはどれか」「一枚のマットで複数のトレーニングができるか」「賃貸でも使える厚さはどれか」などがあります。こうした疑問に対しては、「用途」「安全性」「コスト」「設置性」の観点から比較検討することが重要です。
たとえば、衝撃吸収性や防音性を重視する場合は、EVAやゴムチップ素材を使用した20mm以上の厚手タイプがおすすめです。価格は厚さに比例して上がる傾向にありますが、防音・防振効果と床保護性能を考慮すれば、高い費用対効果が得られます。
現在では、ホームセンターや通販サイトで豊富な選択肢が提供されており、口コミやレビュー情報も充実しています。厚さだけでなく、素材、滑り止め性能、防臭・抗菌加工の有無といった点も含めて総合的に選定することが、満足のいくジムマット選びのポイントとなります。
床補強が不要になるマットの条件とは
ホームジムを設置する際に心配されることの一つに、床への負荷と補強の必要性があります。とくに集合住宅や築年数の古い住宅では、重量器具の設置やトレーニング時の振動が建物に与える影響を懸念されるケースが多く見られます。こうした状況を踏まえて、「床補強が不要になるマット」を選ぶ際の条件を正しく理解することが重要です。
まず第一に、マットの厚さと素材の組み合わせがポイントになります。厚さが20mm以上で、かつ高密度のゴムチップ素材やEVAフォームが使われているマットは、衝撃や振動をしっかり吸収し、建物構造への影響を最小限に抑えてくれます。とくに硬度が65以上ある製品は、バーベルなどの重量器具を使用しても床を傷つけることがなく、床補強を省くことが可能になる場合もあります。
次に重視したいのは設置方法です。単に床に置くだけでなく、ジョイント式マットを使用して床全面をカバーすることで、荷重が広く分散され、局所的な負担を軽減できます。また、マットの下に衝撃吸収シートや防音用のインシュレーターを追加することで、防音効果と床保護力がさらに向上します。
以下に、床補強が不要となるジムマットの条件を表にまとめます。
| 条件項目 | 内容 |
| 厚み | 最低でも15mm以上、理想は20mm以上 |
| 素材 | ゴムチップ、EVA高密度フォーム、業務用PVCなど |
| 設置範囲 | 床全面を覆う大判タイプやジョイント式が理想 |
| 裏面構造 | 滑り止めや防振・吸音効果を持つ加工構造が望ましい |
| 二重構造への対応 | 衝撃吸収マットとインシュレーターなどを組み合わせた多層構造が有効 |
| 耐久性 | 摩耗や変形に強く、長期使用に耐える高耐久仕様 |
また、床の材質や構造に応じたマット選びも大切です。たとえば、フローリングや畳の上では滑りやすくなることもありますので、裏面に滑り止め加工が施されたマットを選ぶことで安全性が高まります。さらに、防音性については「遮音等級L-45以下」を目安に選ぶと、階下への音の伝播を大きく抑えることができます。
床補強を避けたいと考えるユーザーの中には、「ジョイントマットとロールマットではどちらが有利か」「床暖房との併用が可能か」といった疑問もあります。これに対しては、複合素材で作られた三層構造の高性能マットが解決策となります。表面に耐摩耗層、中間にEVAクッション層、裏面に滑り止め層を備えた製品であれば、床へのダメージや音を大幅に軽減することができます。
現在、市場には多様な高機能マットが登場しており、性能と利便性の両立が進んでいます。設置前には必ず床の強度や住環境の制約を確認し、それに応じたスペックのマットを選定することが重要です。結果として、工事を行わずとも、安全で静かにトレーニングできるホームジムを実現することが可能になります。
トレーニングマット・ヨガマット・ストレッチマットとの違いとは?
使用目的別で異なるマットの性能
自宅やフィットネスジムで使用されるマットには、トレーニングマット、ヨガマット、ストレッチマットといった複数の種類があります。それぞれは見た目や素材が似ているように感じられますが、実際には性能や使用目的に明確な違いがあります。この記事では、それぞれのマットの特徴を正確に理解し、目的に合った製品を選ぶための情報をご紹介します。
まず、トレーニングマットは筋力トレーニングや体幹トレーニングなど、高負荷な運動を支えるために設計されています。体重や器具からの衝撃に対応できるよう、厚みは15mm以上が主流で、素材には高密度EVAフォームやゴムチップが使われています。衝撃吸収性や耐久性に優れた構造で、業務用にも採用される品質を備えたモデルが多く見られます。
一方、ヨガマットは、滑りにくさとクッション性のバランスを重視しています。厚さは4mmから8mm程度が一般的で、持ち運びやすく、軽量であることが特徴です。PVCやTPEといった素材がよく使われ、表面には滑り止め加工が施されていることが多いため、安定したポーズ保持が可能です。特に静止を多く含むヨガには適した設計となっています。
ストレッチマットは、柔軟体操や準備運動、またリハビリといった軽度な運動に使われることが多く、厚みは10mm以上、柔らかなウレタンやEVAが使われるケースが多いです。肌あたりが良く、寝転がって使う場面に適していますが、重量器具を使うような高負荷のトレーニングには向いていません。
以下に、それぞれのマットの特徴を比較した表を掲載します。
| 種類 | 推奨厚さ | 主な用途 | 素材例 | 特徴 |
| トレーニングマット | 15〜30mm | 筋力トレーニング、体幹トレーニングなど高負荷運動 | EVA、ゴムチップ | 高耐久、衝撃吸収、防音性、重量器具にも対応 |
| ヨガマット | 4〜8mm | ヨガ、瞑想、軽運動 | PVC、TPE | 滑り止め加工、軽量、持ち運びやすく収納性が高い |
| ストレッチマット | 10〜20mm | 柔軟、準備体操、リハビリなど軽負荷運動 | ウレタン、EVA | 柔らかい感触、肌あたりが優しく寝転がっての使用に最適 |
よくある疑問として、「トレーニングマットとヨガマットは兼用できるのか」「厚みによって運動の効果に違いがあるのか」「一枚のマットで全ての運動に対応できるのか」「滑りやすさや安全性は種類によって異なるのか」「ジム用と家庭用では何が違うのか」などがあります。
これらの疑問に対しては、ご自身の主な運動内容や使用頻度を軸に選ぶことが大切です。たとえば、トレーニングマットは高耐久ですが重く、移動には不便です。ヨガマットは軽量でコンパクトですが、床冷えを防ぐ効果には乏しいです。ストレッチマットは柔軟性に富んでいますが、高重量器具には適していません。
なお、現在では、環境配慮や抗菌性にも優れたTPE素材のヨガマットが非常に注目されています。EVA製のトレーニングマットも、引き続き防音性と衝撃吸収性で高い評価を受けています。ご自身の使用目的に合わせ、レビューや口コミを参考にしながら、最適な一枚を選ぶことがポイントです。
兼用はできる?代用時の注意点
マットを1枚にまとめて兼用することは、スペースやコストの節約という面では魅力的に思えるかもしれません。しかし実際には、用途に合わないマットを使用することで、体への負担が増えたり、トレーニング効果が落ちたりするリスクもあります。
たとえば、トレーニングマットをヨガに使うと、クッション性が高すぎてポーズが安定せず、フォームが崩れてしまうことがあります。反対に、ヨガマットを筋力トレーニングに使うと、厚みや耐久性が足りず、床を傷つけたりマットが破れたりする可能性があります。
それでも兼用を検討する人が多いのは、マットを複数所有するのが難しい、初期費用を抑えたい、使用頻度が高くない、というような理由からです。そうしたニーズに応えるため、ある程度の性能を両立した「汎用マット」も市場には登場しています。
具体的には、厚さ10〜15mmで高密度のEVAフォームを使ったマットであれば、ヨガ、ストレッチ、軽い筋トレにもある程度対応できます。以下に、兼用マットの条件をまとめます。
| 条件項目 | 内容 |
| 厚さ | 10〜15mm(ヨガ〜中負荷の筋トレに対応可能) |
| 素材 | EVAフォーム、TPE(滑りにくく、適度な弾力を持つ) |
| 表面加工 | 滑り止め付きで、抗菌・防臭仕様があると安心 |
| 裏面構造 | クッション性と安定性のバランスがとれた構造が理想 |
| 重量 | 動きにくい適度な重さ(目安として1〜2kg程度) |
兼用時の注意点としては、運動の種類に応じて滑り止めの性能を確認すること、フローリングや畳の上での使用を考慮して裏面の仕様をチェックすること、機器を使う際はマットの耐荷重性を確認することが挙げられます。また、複数人で使用する場合にはサイズと耐久性の両方を見ておく必要があります。
安価なマットには品質にばらつきがあるため、信頼できるブランドの製品やレビュー評価の高いマットを選ぶことをおすすめします。見た目は似ていても、素材の密度や滑り止め性能には大きな差があります。
最終的に、全ての運動に完璧に対応するマットは存在しないと言っても過言ではありません。兼用する場合は、どの運動を最も重視するかを明確にし、その主目的に最適化されたマットを選ぶことが、長期的な満足とパフォーマンス向上につながります。
まとめ
賃貸住宅やワンルームでのトレーニング環境づくりにおいて、ジムマット選びは極めて重要です。近隣への騒音や床の傷、振動の伝わりといった課題を解決するためには、マットの防音性・衝撃吸収性・設置方法を総合的に見極める必要があります。
特に20mm以上の厚手マットは、防振・吸収性能に優れており、ダンベルやバイクなどの重量器具を使用する場合にも安定性を発揮します。防音性能においても、素材によって吸収力に大きな差があり、EVA樹脂やゴムチップ素材は高評価を得ています。また、防音効果はマット単体だけでなく「ジョイントタイプ」「裏面吸着タイプ」「滑り止めパッド」などとの組み合わせによっても左右されるため、総合的な組み合わせを考慮することが重要です。
実際に、去年に実施された住環境機構の調査によると、室内でトレーニング器具を使用している世帯のうち39.6%が「階下・隣室への音や振動が気になる」と回答しており、マット選びが生活の質に直結している現状が明らかになっています。
この記事では、そんな悩みを抱える読者に向けて、各マットの厚みごとの効果やサイズ選び、防音性能の比較、敷き方の工夫などを具体的なデータとともに詳しく解説しました。記事を通じて、マット選びの基準が整理できた方も多いはずです。
誤ったマットを選ぶと、修繕費用やクレーム対応などで数万円の損失につながることもあります。防音や床保護対策は、後回しにせず初期段階から備えることがコスト削減にもつながります。
トレーニングの成果を安心して最大化するためにも、マットの性能を正しく理解し、あなたの住環境に最適な一枚を選びましょう。記事内で紹介した具体例やチェックポイントが、きっとあなたのマット選びの大きなヒントになるはずです。

よくある質問
Q.防音性能が高いジムマットはどの厚みがおすすめですか?
A.賃貸住宅やワンルームでの防音対策には、最低でも15mm以上の厚さが推奨されます。特に20mm以上の厚手タイプは衝撃吸収性と騒音緩和の性能が高く、下階への振動をしっかり抑えることができます。ゴムチップマットやEVA素材を使用した製品は吸収力と静音性に優れており、フィットネス器具の使用時やジャンプを伴うエクササイズにも適しています。床への衝撃やトレーニング音が気になる方には必須の選択です。
Q.ジムマットを敷く広さはどのくらいが理想ですか?1畳では足りますか?
A.使用するトレーニング器具やエクササイズ内容によって異なりますが、一般的なダンベル運動やヨガマット代わりの使用であれば1畳(約90cm×180cm)でも対応可能です。ただし、バーベルベンチやスピンバイクなど大型マシンを使用する場合は2畳(約180cm×180cm)以上、筋トレやHIITを広く行う場合は3畳以上が推奨されます。余裕をもって敷くことで、マットのズレや滑りを防ぎ、安全性も高まります。
Q.ジムマットの掃除や匂い対策はどうすればいい?長く使うためのコツは?
A.ジムマットの掃除には中性洗剤を使った水拭きが基本です。使用後は汗や皮脂汚れを落とし、しっかり乾燥させることでカビや菌の繁殖を防げます。ゴムマット特有の匂いが気になる場合は、風通しの良い場所で陰干しするか、重曹スプレーなど天然素材の消臭剤を併用するのがおすすめです。また、マットの表面を定期的にチェックして摩耗が進んでいないか確認し、異常があれば早めに交換することで安全かつ長く快適に使用できます。
会社概要
会社名・・・GYM&SAUNA
所在地・・・〒150-0034 東京都渋谷区代官山町20-9 サザン代官山B1F
電話番号・・070-8347-5991